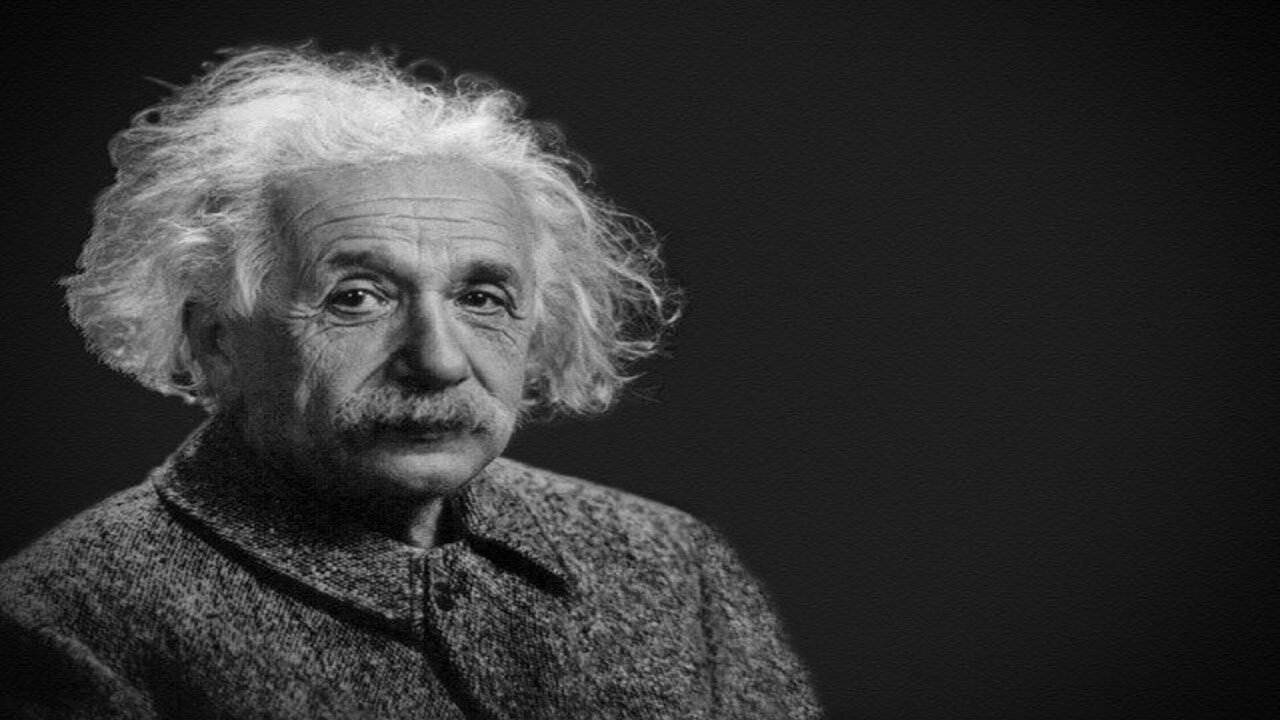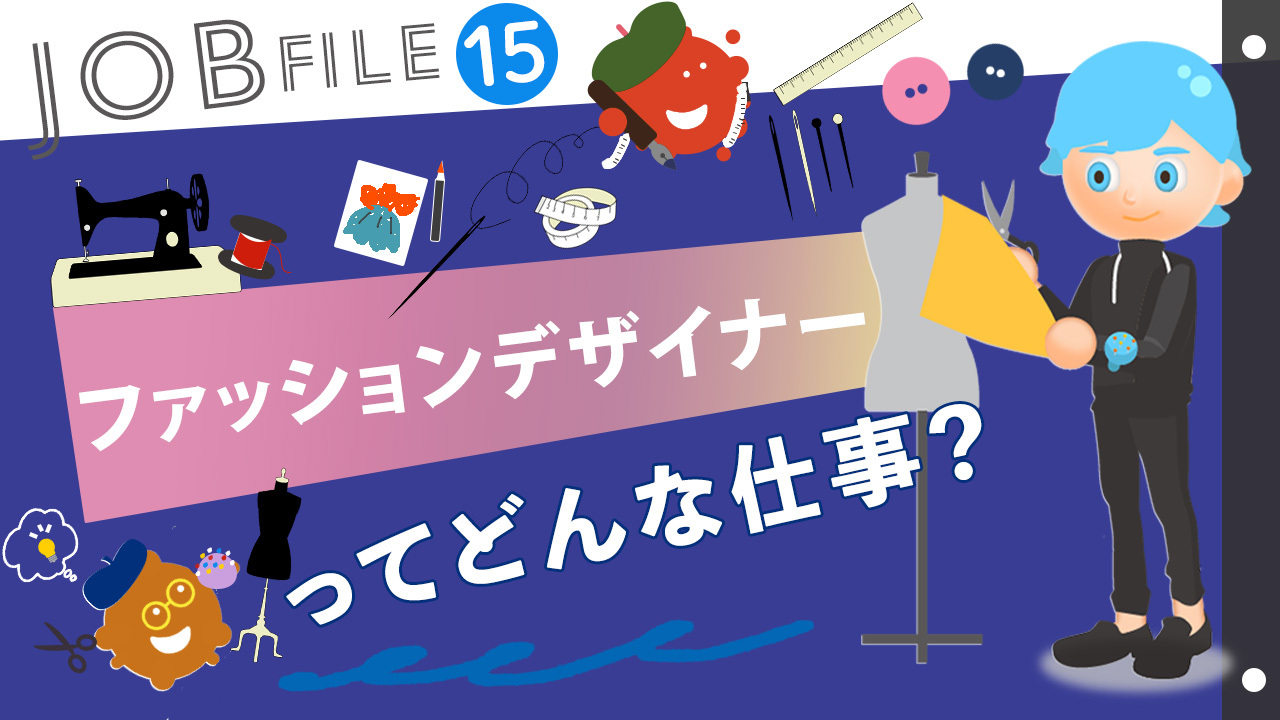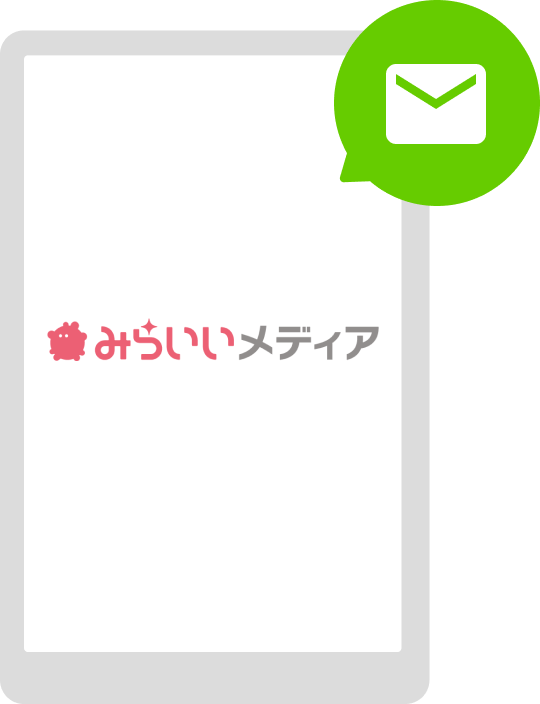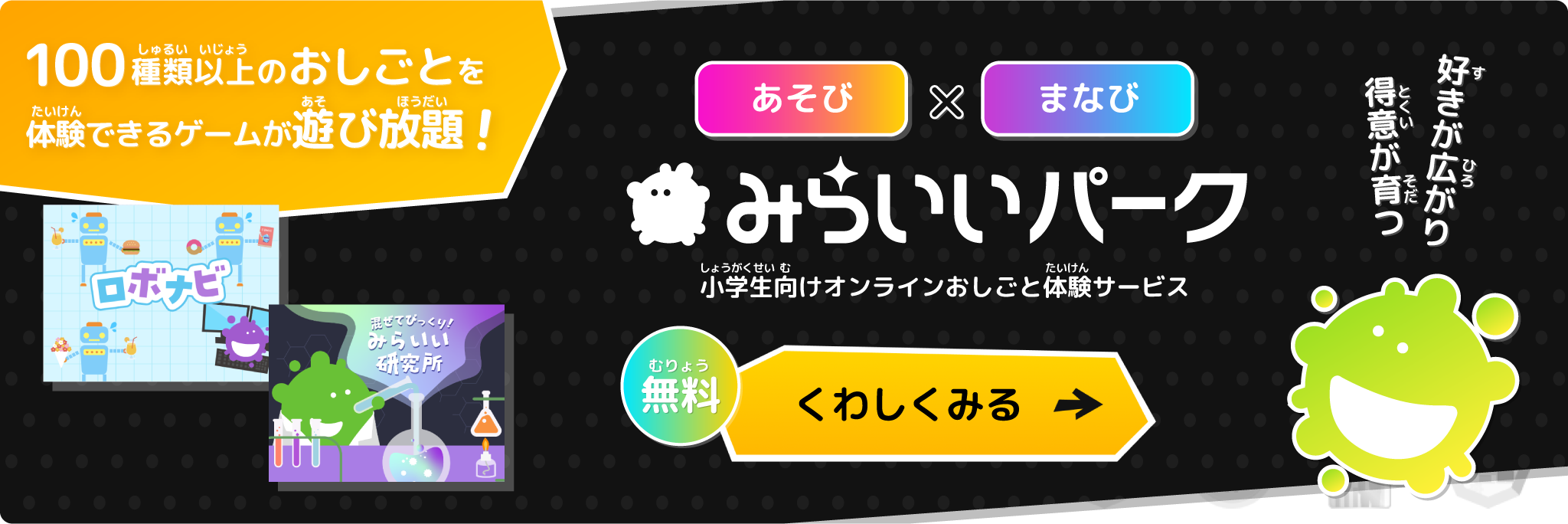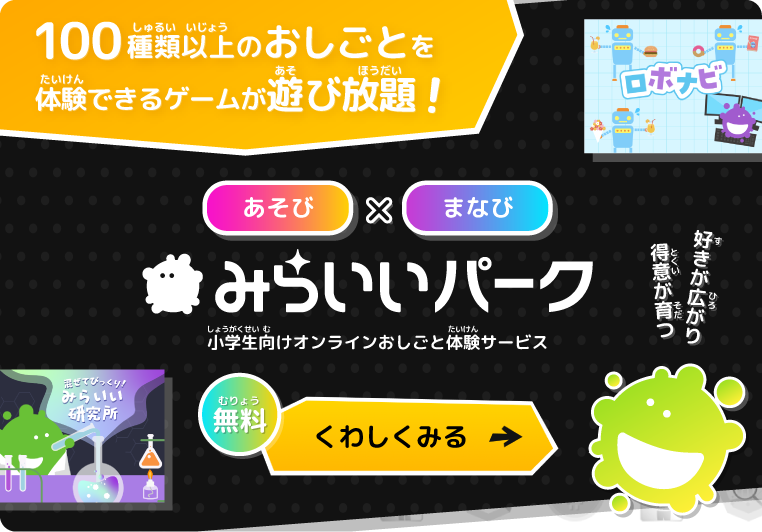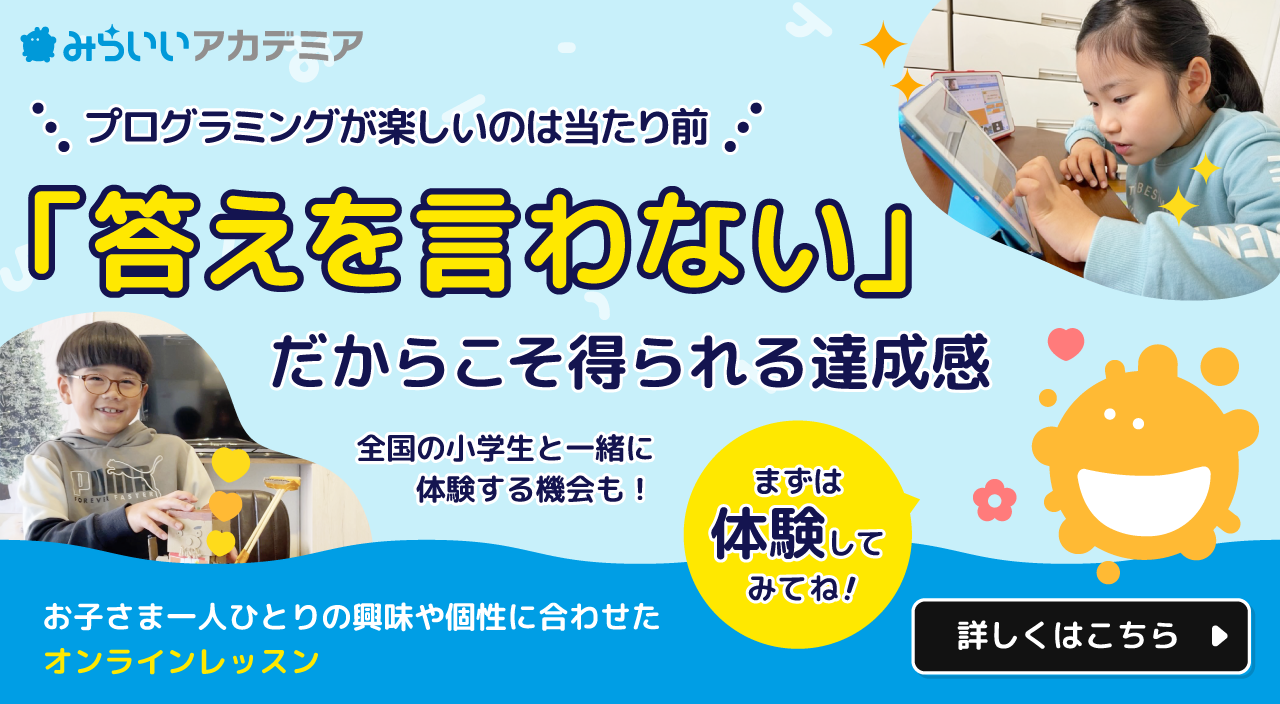ゲームをやめさせたい⁉親が今日からできる小学生に効くルールと工夫は?

現代の小学生にとってゲームは当たり前の娯楽ですが、親としては勉強や生活習慣への影響が心配ですよね。だからといって、いきなりゲームをやめさせるのは逆効果。お子さまと一緒にゲームと上手に付き合う方法を見つけることが大切です。この記事では、どのようなルール決めがいいのかや、やめさせたい時の工夫を紹介します。
ゲームは無理にやめさせるより「上手に付き合う」が大切

現代の子どもたちにとって、ゲームは単なる娯楽というだけでなく友達とのコミュニケーションツールでもあります。完全に排除するのは現実的ではありません。
むしろ、適切なルールを設けて「上手に付き合う」方法を身につけることが、子どもの健全な成長にもつながります。
強制すると親子関係が悪化するリスクも
「ゲームは絶対にダメ」と頭ごなしに禁止してしまうと、子どもは隠れてゲームをするようになったり、親に対して反発心を抱いたりする場合があります。
特に小学校高学年になると、友達の間でゲームの話題が出るでしょう。
そんな中、完全にゲームを禁止してしまうと、友達関係において孤立感を感じる場合もあるかもしれません。
親の意見だけで決めてしまうのではなく、まずはお子さまとの対話が大切です。まずは「どんなゲームをしているの?」と寄り添う形で話しかけてみてましょう。
小学生が熱中しやすい理由は?
ゲームは小さな達成感を継続的に与えるように設計されています。
「もう少しで次のレベルに上がる」「あともう少しで課題をクリアできる」といった報酬システムが脳を刺激し、子どもたちが熱中しやすいように作られています。
また、現代の小学生にとってゲームは友達との重要な関係構築ツールでもあります。
「昨日のゲームの続きを一緒にやろう」「新しいキャラクターを手に入れたよ」といった会話が、友情を深めるきっかけになっている場合もあるようです。
ゲーム=悪ではなく「使い方・時間の管理」が大切
ゲーム自体が悪いものではなく、問題となるのは「使い方」や「時間の管理方法」です。
適切なルールのもとでゲームを楽しむと、集中力や問題解決能力、チームワークなどの能力を育めます。
ここで重要なのは、ゲームをうまく活用するためのルール作りと、それを継続する工夫です。
「ゲームをやめさせたい」と感じる理由と課題

なぜ保護者は「ゲームをやめさせたい」と感じるのでしょうか。
自分の考えや気持ちを整理すると、対応策も見つけやすくなります。一緒にみていきましょう。
勉強や生活習慣への支障
ゲームをやめさせたいと最も多く感じる理由が、勉強や生活習慣への悪影響です。
たとえば「宿題をやる前にゲームを始めて、結局夜遅くまでかかってしまう」「朝起きられずに学校に遅刻しそうになる」「食事の時間になってもゲームをやめられない」というものです。
特に算数の計算問題や漢字の練習など、継続的な学習が必要な分野では、ゲーム時間が長くなると、学習時間が削られ、成績に影響が出る可能性があります。
また、夜遅くまでのプレイで睡眠不足になり、翌日の授業に集中できないという悪循環に陥ってしまうかもしれません。
こういった状況はお子様の将来にも影響が出るため、保護者はゲームに対して不安を感じると考えられます。
依存への不安
「このままではゲーム依存症になってしまうのでは」という不安を抱く保護者も多くいます。
実際に、夜中まで隠れてゲームをする、ゲームのことばかり考えている、ゲームを注意されると激しく怒る、といった行動が見られると、親としては心配になるのは当然です。
特に最近のオンラインゲームには終わりがなく、友達と一緒にプレイすることも多いため、「みんなが待っているから」「今やめると迷惑をかける」という理由でずるずると続けてしまう場合があります。
こうした状況が続くと、自分でゲーム時間をコントロールするのは難しくなってしまいます。
親がイライラして自己嫌悪になる悪循環
仕事で疲れて帰ってきたときに、宿題もせずにダラダラとゲームをしている子どもの姿を見て、つい感情的になったことはありませんか。
「何度言ったらわかるの!」と怒鳴ってしまった後に「また怒ってしまった」と自己嫌悪に陥る人も多いですよね。
また、忙しい日々の中で「静かにしていてほしい」という理由でゲームをさせてしまい、後から「また甘やかしてしまった」と罪悪感を抱くことも。
こうした感情の起伏が続くと、保護者も辛いですよね。
そうなる回数を減らすためにも、ゲームをする時には、ルールを定めておくのが重要です。
ゲームをしている時、子どもたちの姿勢も気になるところ。良い姿勢とはどのような状態か、家庭でできる筋力UPの方法も解説しています。
小学生の姿勢が悪くなってしまうのはなぜ?よい姿勢のメリットや親子でできる筋力UPの方法もご紹介!
今日からできる!現実的なルールと工夫

ゲームと健全な関係を築くために、親子で実践できる現実的なルールを設けましょう。重要なのは、親が一方的に決めるのではなく、子どもと一緒に話し合って決めることです。
家庭でのルールを一緒に決める
効果的なルール作りの第一歩は「子どもを交えた家族会議を開く」です。
- ゲームは宿題が終わってから
- 平日は1時間まで、休日は2時間まで
- 課金は月1000円まで
などといったルールを、なぜそのルールが必要なのかを説明しながら一緒に決めていきます。
子ども自身も納得していると、ルールを守ろうという意識が高まります。
たとえば「宿題をやらないと翌日の授業についていけなくなるかもしれない」「夜遅くまでゲームをすると朝起きられなくなるから、何時にやめる?」といった問いかけをして、子ども自身に考えさせることも重要です。
また、自分との約束を守ることは自己肯定感の向上にもつながります。もし約束を破ることが普通になってしまうと、子どものセルフイメージが「約束も守れない自分」になってしまうことも。たかがゲームの約束と思わず、決めたことを守れるサポートをしてあげましょう。
タイマーやペアレンタルコントロールを活用する
ルールを決めても、夢中になっていると時間を忘れてしまうもの。
そこで有効なのが、タイマーやペアレンタルコントロール機能の活用です。
キッチンタイマーを使って「あと10分で終わりだよ」と声をかけたり、ゲーム機の設定で自動的に時間制限をかけたりすることで、子どもも時間を意識しやすくなります。
声のかけ方も「もうやめなさい!」ではなく、「タイマーが鳴ったから、約束通り終わりにしようか」といった具合に、感情的にならないようにするのがポイントです。
「順番ルール」や「ご褒美ルール」で納得感を持たせる
より効果的なルール作りのために「順番ルール」や「ご褒美ルール」を導入してみましょう。
順番ルールとは「宿題→習い事の練習→ゲーム」といった具合に、やるべきことの優先順位を明確にする方法です。
ご褒美ルールは「勉強を30分頑張ったらゲームを30分できる」「宿題を忘れずに全部できたら、週末は3時間ゲームしてもいい」といったように、努力に対する報酬としてゲーム時間を設定するルールです。
ただし、ご褒美ルールには、勉強を頑張りすぎて、結果的にゲーム時間が長くなりすぎるのを防ぐために「1日最大2時間まで」などと、上限を設けましょう。
親も一緒に「デジタルオフ時間」を設ける
子どもにゲームの時間制限を求めるなら、親も一緒にデジタル機器との付き合い方を見直すのも大切です。
夕食の時間や寝る前の1時間は、家族全員がスマートフォンやタブレットを使わない「デジタルオフ時間」を設けてみましょう。
子どもに「ゲームはだめ」と言いながら、親がスマートフォンをずっと見ていては説得力がありません。
家族みんなでデジタル機器から離れる時間を作ると、コミュニケーションの機会も生まれます。
小学生にゲームをやめさせたいときの工夫
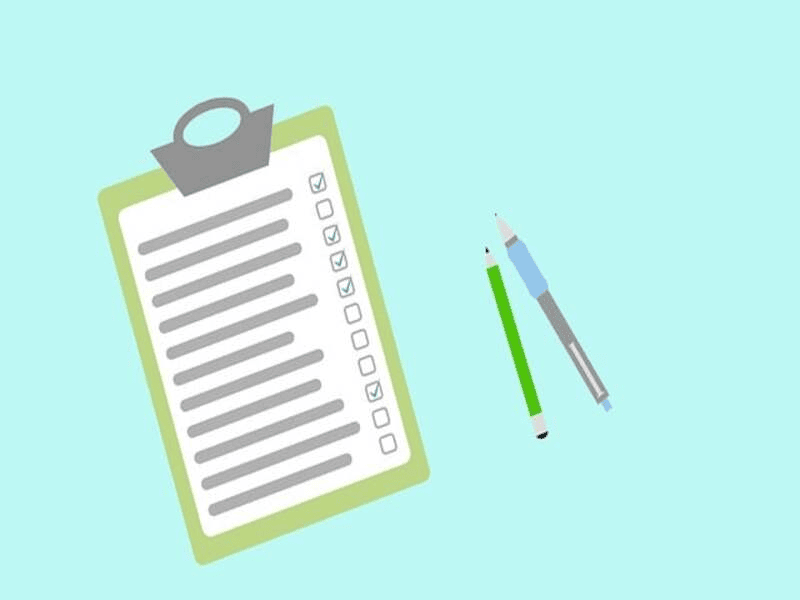
基本的なルールを設けた上で、さらに工夫ができると、子どもが自主的にゲームとの健全な関係を築けるようになります。
ルールを紙に書いて一緒にサインする
決めたルールは口約束だけでなく、紙に書いて親子でサインをしてみましょう。
「我が家のゲームルール」として、
- 平日は宿題後に1時間
- 夜9時以降はゲーム禁止
- ルールを破ったら翌日はゲーム禁止
といった内容を明記し、冷蔵庫や子ども部屋に貼っておきます。
目に見える形でルールを共有すると、子どもも約束を意識しやすくなります。
また、ルールを破ってしまったときも「約束したよね」と感情的にならずに指摘できるため、親のストレス軽減にもつながります。
外遊び・習い事など「代替行動」を増やす
ゲーム時間が長くなる原因の一つが「他にやることがない」という状況です。
特に雨の日や冬の時期は外遊びも限られるため、自然とゲーム時間が増えてしまいがちです。
そこで重要なのが、ゲーム以外の魅力的な選択肢を用意する方法です。
近所の公園に一緒に出かける、図書館で本を借りる、料理や工作を一緒に楽しむ、友達と約束して外で遊ぶ、習い事を始めるといった代替行動を増やしましょう。
忙しい毎日の中で毎回付き合うのは大変ですが、週末だけでも一緒に過ごす時間を作ると、子どもの興味をゲーム以外に向けられます。
ゲームでイライラしたときは「一時中断ルール」で切り替える
ゲームをしているとき、思うようにいかずにイライラして暴言を吐いたり、コントローラーを投げつけたりする行動が見られる場合があります。
このような状況では、感情が高ぶっているため話し合いも困難です。
そんなときは「一時中断ルール」を発動させましょう。
「イライラしているときは一度ゲームから離れて、5分間深呼吸をする」「怒りが収まったら再開してもいい」といったルールを事前に決めておくことで、子どもも冷静さを取り戻す時間を作れます。
親の心理ケアも忘れずに
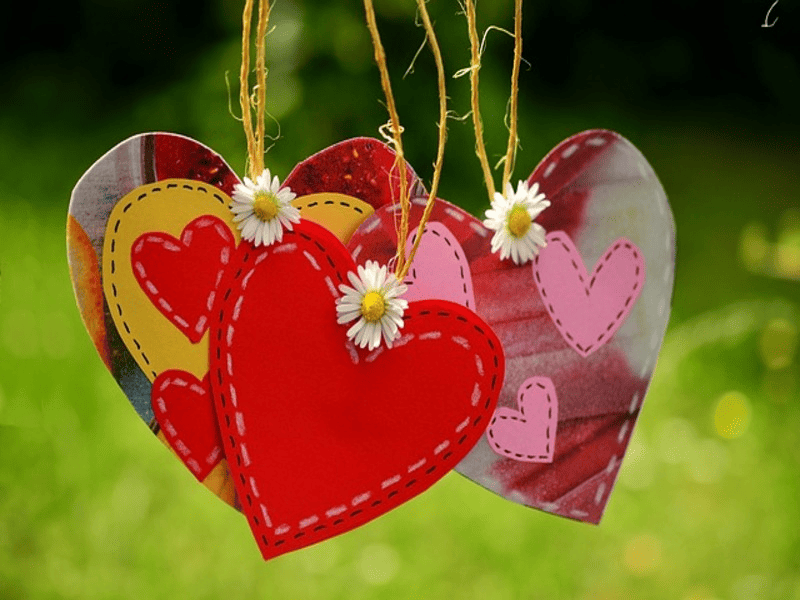
ゲームを巡る親子のやりとりは、保護者にとっても大きなストレスとなります。
ゲームと上手に付き合っていくためには、親自身の心のケアも欠かさずに行いましょう。
「叱る」と「怒る」の違いを意識
「怒る」は親の感情を子どもにぶつける行為であり、「叱る」は子どものことを思って改善点を伝える行為です。
たとえば「何度言ったらわかるの!いい加減にしなさい!」は怒っている状態です。
一方「約束の時間を過ぎているよ。宿題が終わらないと明日困るから、今日はここで終わりにしよう」は、叱っている状態です。
子どもの将来を思っての指導としての「叱る」を意識すると、感情的に怒って反省することも減らせます。
感情的にならないための6秒ルール・深呼吸
イライラが頂点に達したときは、まずは6秒間待つよう心がけてみましょう。
感情の激しい波は6秒程度でピークを過ぎると言われており、この時間を意識的に作ると冷静さを保ちやすくなります。
深呼吸も効果的です。
「3秒で息を吸って、6秒で息を吐く」を3回繰り返すだけでも、心拍数が落ち着き、感情をコントロールしやすくなります。
子どもの前で深呼吸をしても構いません。
「お母さん(お父さん)も落ち着こうと思っている」という姿勢を見せるのは、子どもにとっても良いお手本になります。
一貫性を持った伝え方で安心感を与える
日によって言う内容が変わってしまうと、子どもは混乱し、ルールの意味を理解しにくくなります。
「今日は疲れているから仕方ない」「今日だけ特別」といった例外を頻繁に作ってしまうと、ルール全体の効果が薄れてしまいます。
一貫性を保つためには、夫婦や家族間で方針を共有するのも重要です。
お母さんは厳しくルールを守らせるのに、お父さんは甘い、といった状況では子どもも困惑してしまいます。
事前に家族で話し合い、同じ方向性で子どもと向き合うことが子どもにとっての安心感につながります。
子どもへ声をかけてもなかなか動いてくれない。その行動の本音についてこの機会に理解を深めてみませんか?コーチングマスターが今すぐ使える声かけの方法を伝授しています。
「今やろうと思ってたのに・・・」それ何回目?動かない子ども、本当はどう思ってるの?(教えて!マスターRiku Vol.4)
依存が心配なときのチェックと相談先

適切なルール作りや工夫を試してみても改善が見られない場合や、より深刻な依存の兆候が見られる場合は、専門機関への相談も検討しましょう。
ゲーム依存のサイン
世界保健機関(WHO)は2019年に「ゲーム障害」を疾病として正式に認定しました。
以下のような兆候が長期間(12ヶ月以上)続く場合は、専門的な支援が必要かもしれません。
- 生活リズムの完全な崩壊(昼夜逆転、食事を取らない)
- 学校を休んでまでゲームをする
- ゲームをやめるように言うと激しく攻撃的になる
- 現実とゲームの区別がつかなくなる
- 隠れてゲームをするようになった
- 友達との関係よりもゲームを優先するようになった
- 家族とのコミュニケーションを完全に拒否するようになった
子どもの様子をみながら、必要な場合には、専門家を頼るようにしましょう。
学校や地域の相談窓口を活用
ゲーム依存について相談しやすいのは、学校のスクールカウンセラーや養護教諭です。
各自治体には「青少年相談センター」や「子育て支援センター」といった相談窓口もあります。
これらの窓口では、ゲーム依存に関する相談を受け付けており、必要に応じて専門機関への紹介もしてもらえます。
まずは電話相談から始めることもできるため、不安な時こそ気軽に利用してみましょう。
専門機関や医療機関への相談も選択肢に
より専門的な支援が必要と判断される場合は、精神科やメンタルクリニックへの相談も検討しましょう。
ゲーム依存の背景には、学校でのストレスや発達の特性、家族関係の問題など、様々な要因が複合している場合があります。
専門医による診断や心理カウンセラーによるサポートを受けると、根本的な原因にアプローチした治療が可能になります。
これらの相談窓口を上手に活用しながら、最終的には子どもが自立してゲームと付き合えるようになることが目標です。
「ゲームをやめさせたい」ときの行動ステップ
すべてを一度に実行するのではなく、できることから少しずつ始めてみましょう。
- 家族でルールを決め、紙やアプリで可視化
子どもと一緒に話し合い、納得できるゲームルールを作成する。紙に書いて見えるところに貼ったり、ペアレンタルコントロール機能を設定したりして、ルールを「見える化」することが重要。
- ゲーム以外の選択肢を一緒に楽しむ
外遊びや読書、料理、工作など、ゲーム以外の魅力的な活動を子どもと一緒に体験する。
- 親も一緒に「デジタル時間」を見直す
子どもだけでなく、家族全員でデジタル機器との付き合い方を見直しましょう。
- 必要なら専門機関に相談する
家庭での取り組みだけでは改善が見られない場合や、依存の兆候が心配な場合は、迷わず専門機関に相談しましょう。学校のスクールカウンセラー、自治体の相談窓口、医療機関など、様々な選択肢があります。
ゲームとの健全な付き合い方を身につけることは、現代の子どもたちにとって重要なライフスキルの一つです。親子で協力しながら、バランスの取れた生活を目指していきましょう。
お子さまの健全な成長をサポートする「みらいいパーク」
みらいいでは、お子さまの「なりたい」「やりたい」に合わせて楽しめる40種類以上のお仕事体験ゲームをご用意しています。
ゲーム以外にも夢中になれることを見つけたり、将来の可能性を広げたりするきっかけとして、ぜひ「みらいいパーク」をご活用ください。
ゲームとの健全な付き合い方を学びながら、お子さまの興味関心を広げるサポートをいたします。
プログラミングだけじゃない!体験から子どもたちの自立を促すオンラインプログラミングスクール「みらいいアカデミア」

%20(1).jpg)






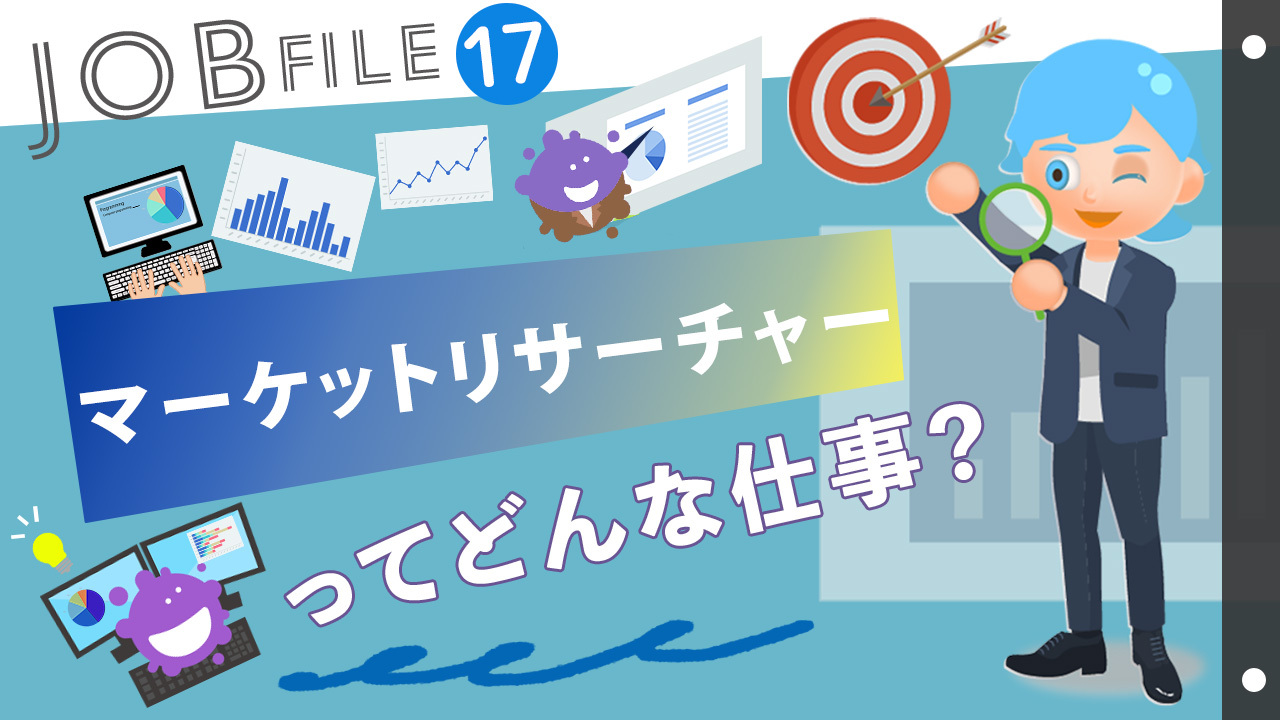
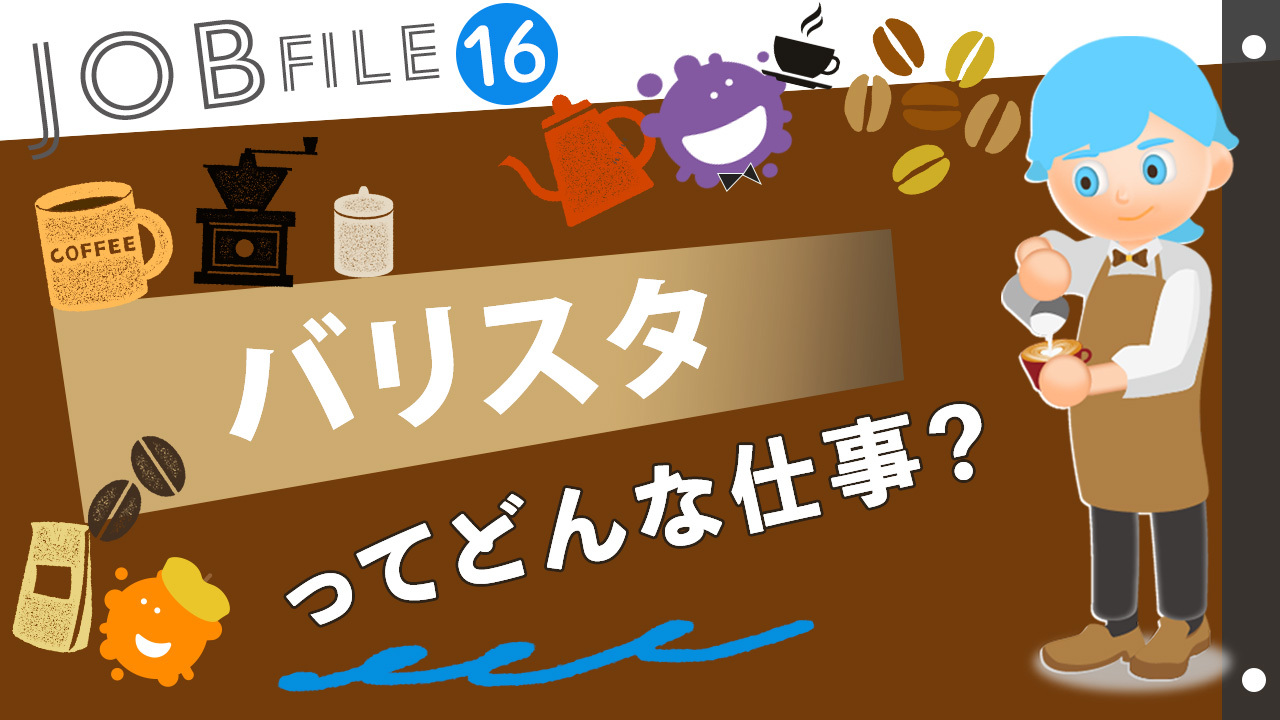

%20(1).jpg)